「この子たちが、自分の言葉で語り、自分の考えを出し合う場をつくりたい。」
そう願いながらも、現実の教室では――
「発言する子ばかりが話す」
「空気を読んで黙る子がいる」
「意見をぶつけ合うと雰囲気が悪くなる」
そんな悩みを抱えていませんか?
読んでくださりありがとうございます。
17年目の小学校教員として、これまで数多くの学級経営に関わってきました。今日は、「心理的安全性が高まる学級経営」に欠かせない5つの声掛けをお伝えします。
1. 「それ、どういう意味?」
子どもたちは“評価”に敏感です。
先生の「それ、いいね!」という言葉も、時に“正解”を示すように受け取られてしまうことがあります。
大切なのは、「価値づけ」より「理解の姿勢」。
たとえばこんな声掛けです。
「なるほど。そう思った理由をもう少し聞かせてくれる?」
「○○さんが言ったのって、どういうこと?説明して」
子どもに「自分の考えを聞いてもらえた」という安心感を与えることが、心理的安全性を高める第一歩です。
2. 「わからない」の価値づけ
授業で「わからない」と言える雰囲気があるクラスほど、学び合いが深まります。
でも現場では、「わからない」が恥ずかしい空気になっていることも少なくありません。
だからこそ、先生の一言が大切です。
「わからないって言えるのが先生の授業では一番値打ちがある。」
「わからないっていうのは、わかりたいってことだよ。」
「できる子」「わかる子」だけが注目される教室では、子どもたちは“逃げ道”を探します。
でも「わからない」が尊重される教室では、子ども同士の関わりが自然と生まれていきます。
3. 「真ん中に置こう」
学級経営における環境設定も、「心理的安全性」を左右します。
たとえば私は授業中、こう伝えています。
「みんなで話し合うときは、ノートや意見カードを真ん中に置こう。」
これは単なる物理的な配置ではありません。
“学びの中心を共有する”というメッセージでもあります。
ものを真ん中に置く。指差しをする。隣の人を見る。
この小さな行動の積み重ねが、「学びから逃げない」仕組みをつくるのです。
4. 「ゆっくりでいいよ」——焦らず、信じて待つ
教員として17年。
「早くできるようになってほしい」という気持ちは、何度も湧いてきました。
でもその「早く」は、先生側の都合であることが多いのです。
子どもたちは、それぞれ違うペースで育ちます。
「やる子」「やらない子」
「できる子」「できない子」
どの子にも、その子なりの理由があります。
だから私は、こう伝えるようにしています。
「ゆっくりでいいよ。ゆっくりこそが、いちばん早いんだ。」
公立小学校だからこそ、“みんなで育つ”を大切にしたい。
焦らず、待つこと。それが心理的安全性の土台になります。
5. 「全部正解で、全部不正解」——多様な価値を認める
教室では、子どもの意見が多様になることがあります。
でもその時こそチャンスです。
先生が「どっちが正しいか」を決めてしまうと、学びは止まります。
だからこそ私は、こんな言葉をよく使います。
「全部正解で、全部不正解かもしれないね。」
この言葉は、子どもたちに
「いろんな考え方があっていい」
「正解、不正解ではなくて、ちがいだね」
と伝えます。
その結果、子どもたちは自分の意見に自信を持ち、相手の考えも尊重するようになります。
🌱まとめ:心理的安全性は、声掛けから始まる
心理的安全性の高い学級経営には、特別なスキルよりも「言葉の選び方」が重要です。
今日紹介した5つの声掛けは、どれも小さなことばかり。
でも、これらが積み重なることで、子どもたちは安心して学び、意見を交わすようになります。
- 「それ、どういう意味?」
- 「わからないって言えるの、すごいね。」
- 「真ん中に置こう。」
- 「ゆっくりでいいよ。」
- 「全部正解で、全部不正解。」
“朝の15分”で、学級経営を整える
もしあなたが今、
「子どもとの関わりに迷いがある」
「もっと安心できる教室づくりをしたい」
と思っているなら、ぜひ私が運営するオープンチャット【教員朝活】に参加してみてください。
毎週水曜日の7:15~7:30
学級経営・心理的安全性・コーチングなどのテーマに僕の経験や気づきを発信しています。
一人では見えない視点が、仲間と出会うことで見えてきます。
▼ オープンチャット参加はこちらから▼
焦らず、比べず、信じて待つ。
それが、子どもの育ちも先生の育ちも支える“最速の道”です。
-1.png)
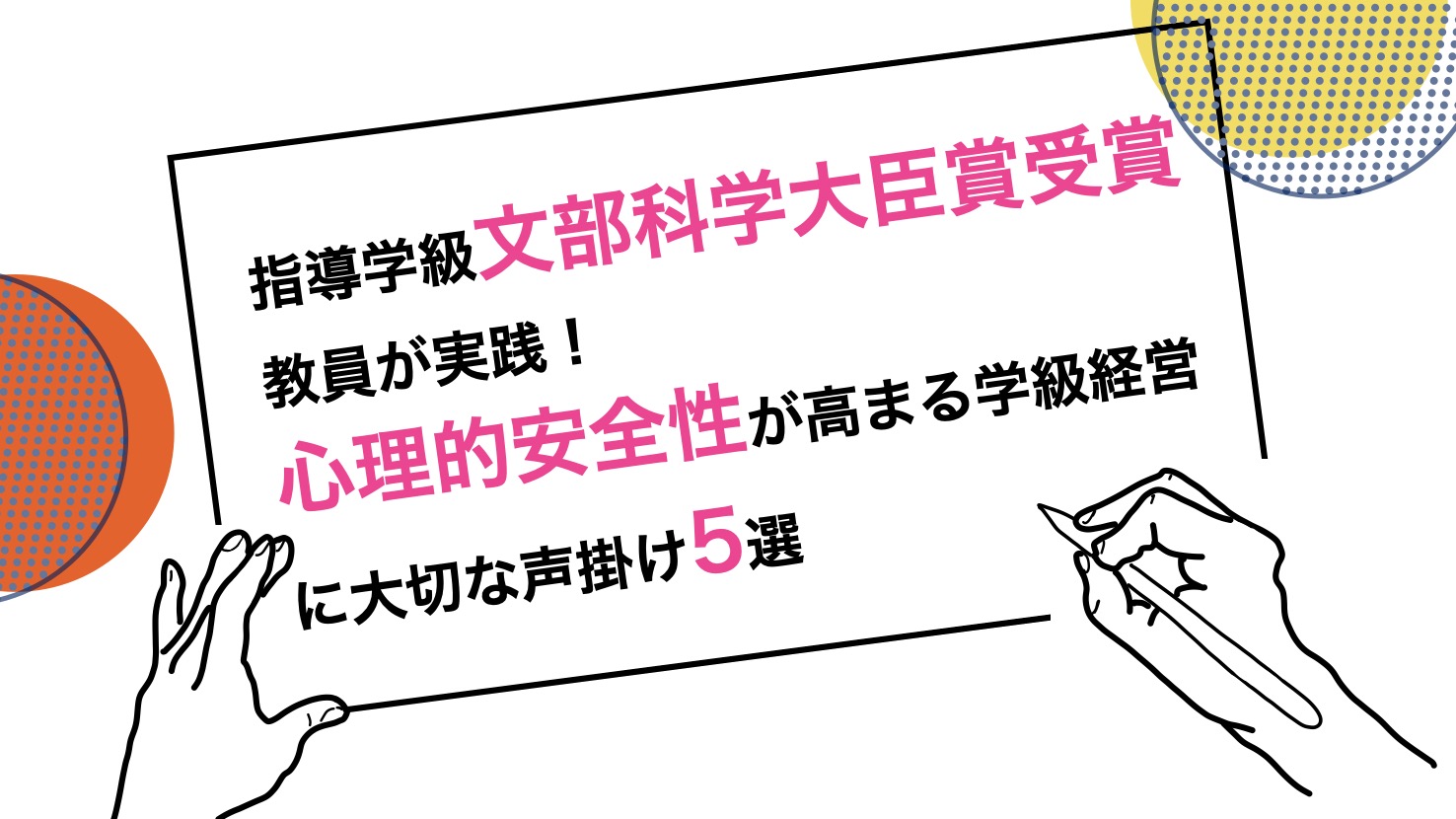

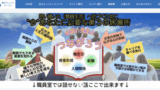
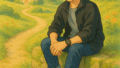
コメント