子育てをしていると、どうしても叱らなければならない場面が出てきます。
3歳までは「叱らない育児」。なんてことも聞きますが実際は…
おもちゃを投げたり、危ない場所に走って行ったり、兄弟げんかをしてしまったり…。
そんなとき「どう叱ればいいんだろう」「自己肯定感を傷つけないか心配」と迷う気持ち、私自身もよく感じます。
でも「してはいけないこと」「やめて欲しいこと」を伝える必要があるとき、時と場合によって親も試行錯誤の毎日。そんな時は少し意識を変えるだけで、叱ることが「ダメな経験」ではなく「信頼関係や自己肯定感を育てる経験」になることがあるのだと気づきました。
ここでは、私が実際に大切にしてきたことや、日々の中で感じた工夫をまとめてみます。
「叱る」前にあるのは信頼関係
叱り方そのものよりも大事だなと思うのは、親子のあいだにある信頼関係です。
子どもが「自分のことを分かってもらえている」と感じられていれば、親の言葉は安心して届きます。でもその土台が揺らいでいると、同じ言葉でも「否定された」「嫌われた」と受け取ってしまうことがあるんですよね。
信頼関係は特別なことではなく、日常の中のほんの小さな積み重ねだと思います。
子どもの話を最後まで聞いてみる
「ありがとう」と素直に伝える
一緒に笑う時間を持つ
こうした何気ないやりとりが、叱る場面でも「大切に思ってくれているから言ってくれているんだ」と子どもが感じられる土台になるのかなと感じています。
自己肯定感を守り、育てる叱り方 2つのポイント
それでも実際に叱らなければならないときはありますよね。私自身が意識しているのは、
①「子どもの存在そのものを否定しないで、行動だけを伝えること」です。
「おもちゃを投げると危ないよ」
「叩かれるとお友だちが痛いんだよ」
こんなふうに伝えると、子どもも「自分がダメ」なのではなく「行動がよくなかった」と分かりやすいように思います。
②叱る前に「気持ちを受け止める」ことも大事にしています。
「遊びたかったんだよね。でもこれは危ないからやめよう」
「嫌だったんだよね。けど叩かれると相手が痛いんだよ」
気持ちを一度受け止めてもらえると、子どもは安心して次の言葉を聞けるんですよね。
それから、叱るときはできるだけ短く、具体的に。長いお説教は結局届かないことが多くて、「ここは走らないよ」「順番を待とうね」とシンプルに言った方が伝わりやすいと実感しています。
叱ったあとのフォローでつながりを回復
私が特に意識しているのは、叱ったあとにフォローを入れることです。
叱りっぱなしだと、子どもは「嫌われた」と感じてしまいがち。でも「でも、ちゃんと話を聞けたね」「次はできそうだね」と伝えると、子どもは「自分はダメ」ではなく「成長できる存在なんだ」と受け止めてくれる気がします。
私自身、つい強く叱りすぎてしまったときには、「さっきは怒りすぎちゃったね。でも大切だから言ったんだよ」と伝えるようにしています。完璧ではないけれど、親の気持ちを素直に伝えることが信頼を回復する一歩になると思っています。
日常でできる信頼関係の積み重ね
叱る場面に備えて…というより、普段からの積み重ねが大切だなと感じます。
スキンシップを増やす:抱っこやハグは「安心していいんだ」というサインになります。
小さな成功を喜ぶ:「着替えられたね」「手伝ってくれて助かった」と言葉にするだけでも大きな自信になります。
一緒に笑う:ただ笑い合う時間は、叱ったときに効く“心の貯金”になると実感しています。
まとめ ― 叱ることも信頼を深める時間
子育てをしていると、「叱らなきゃ」「でも傷つけたくない」と葛藤することばかりです。私自身も感情的に叱って後悔する日がまだまだあります。
でも、いいなと思えることを工夫して伝えたり、日常のやりとりを大切にしたりすることで、叱ることは決してマイナスだけではなく、信頼関係や自己肯定感を育むきっかけにもなると感じています。
完璧である必要はなくて、あとから「言いすぎちゃった、ごめんね。でも大切に思っているから伝えたんだよ」と言えれば、それで十分なんだと思います。
子どもと一緒に悩みながら、少しずつ関係を育てていければいい。そんなふうに思いながら、私も日々の子育てに向き合っています。
-1.png)
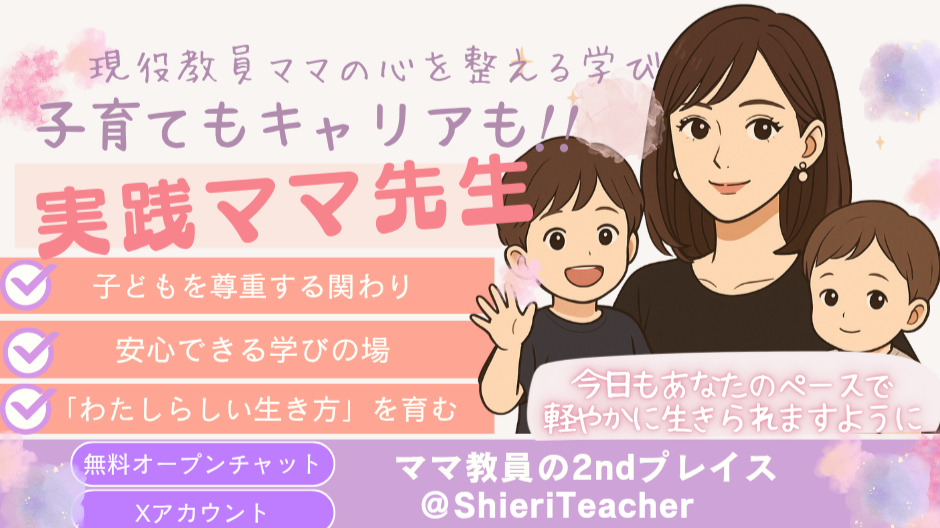

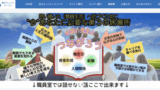
コメント