「もう限界かも」「学校に行きたくない」――そう感じる朝は、決してあなただけではありません。教員の仕事は、人の心と向き合う大変さがあるからこそしんどいと感じる瞬間が誰にでもあります。この記事では、現場と教育センター双方の視点から、しんどいときの考え方と相談できる先、そして心を守る方法をまとめます。
教員が「しんどい」と感じるのは自然なこと
しんどさは弱さではなく、責任感の裏返しです。若手教員ほど「全部を完璧に」と抱え込みやすく、知らないうちに消耗します。まずは自分の状態を言語化し、「一時的なしんどさ」と「続くしんどさ」を分けて捉えましょう。
よくある“しんどい”要因
- 授業が空回りしている感覚が続く
- 保護者対応や同僚関係へのプレッシャー
- 準備時間の不足・持ち帰り仕事の常態化
- 「自分は向いていないのでは」という自己否定
しんどいとき、誰に相談すればいい?
「迷惑かけたくない」「弱音に見られたくない」――そんなブレーキが相談を遠ざけます。しかし、言葉に乗せた時点で負荷は軽くなります。到達しやすい順に3つの相談先を示します。
① 校内の信頼できる先生へ
- 同学年の先生/学年主任/養護教諭など“日常を見ている人”
- 「解決策をもらう」よりも「聴いてもらう」で十分価値あり
② 管理職・教育センターの相談窓口
- 近年は管理職も教職員のメンタルケアを重視
- 教育センターには守秘義務の下で相談に乗る専門職が配置
③ 匿名・オンラインの活用
- 教職員向けメンタルヘルス相談(電話/オンライン)
- SNSコミュニティやテキストベースのカウンセリング
- 「顔を出さずに文字で話す」だけでも孤立感は薄れる
相談しても状況が変わらない…と感じたら試す3つのセルフケア
1) 「完璧」をやめて“80点でよし”を許可する
すべてを100点にしようとすることには、無理があります。優先順位を決め、「今日はここまで」を意図的につくることで回復の余白を確保します。
2) 感情ログを1行だけ書く(可視化)
ノートやスマホに「今日しんどかったこと/よかったこと」を各1行書くのもよいでしょう。
例)「授業で指示が通らずイライラ/放課後に子どもが『ありがとう』で救われた」
可視化により“自分全体=ダメ”という認知をほぐせます。
3) “他人の物差し”を手放す
同僚やSNSの成功体験と比較し続けると、努力が苦痛に変わります。あなたにしかできない関わり方に焦点を戻しましょう。それぞれの先生方で性格もキャラクターも大事にしたいことも違います。自分の強みを生かすことを大切に。
「相談する」は弱さではなく、強さです
教員文化には「我慢」が根強い一方、助けを求める力はプロの力です。相談は自分を守るだけでなく、子どもたちに「頼る力」を背中で示す行為でもあります。もし今がしんどいなら、今日、だれか一人にメッセージを送ってみてください。
まとめ:一人で抱えない。小さな相談が、明日を守る
- しんどいのは自然な反応。まずは状態を言語化しましょう。
- 相談先は「校内 → 公的 → 匿名」と階段的に行なってみる。
- 完璧主義を緩め、感情を見える化し、比較しない。
あなたの小さな一歩が、明日の笑顔を守ります。
-1.png)
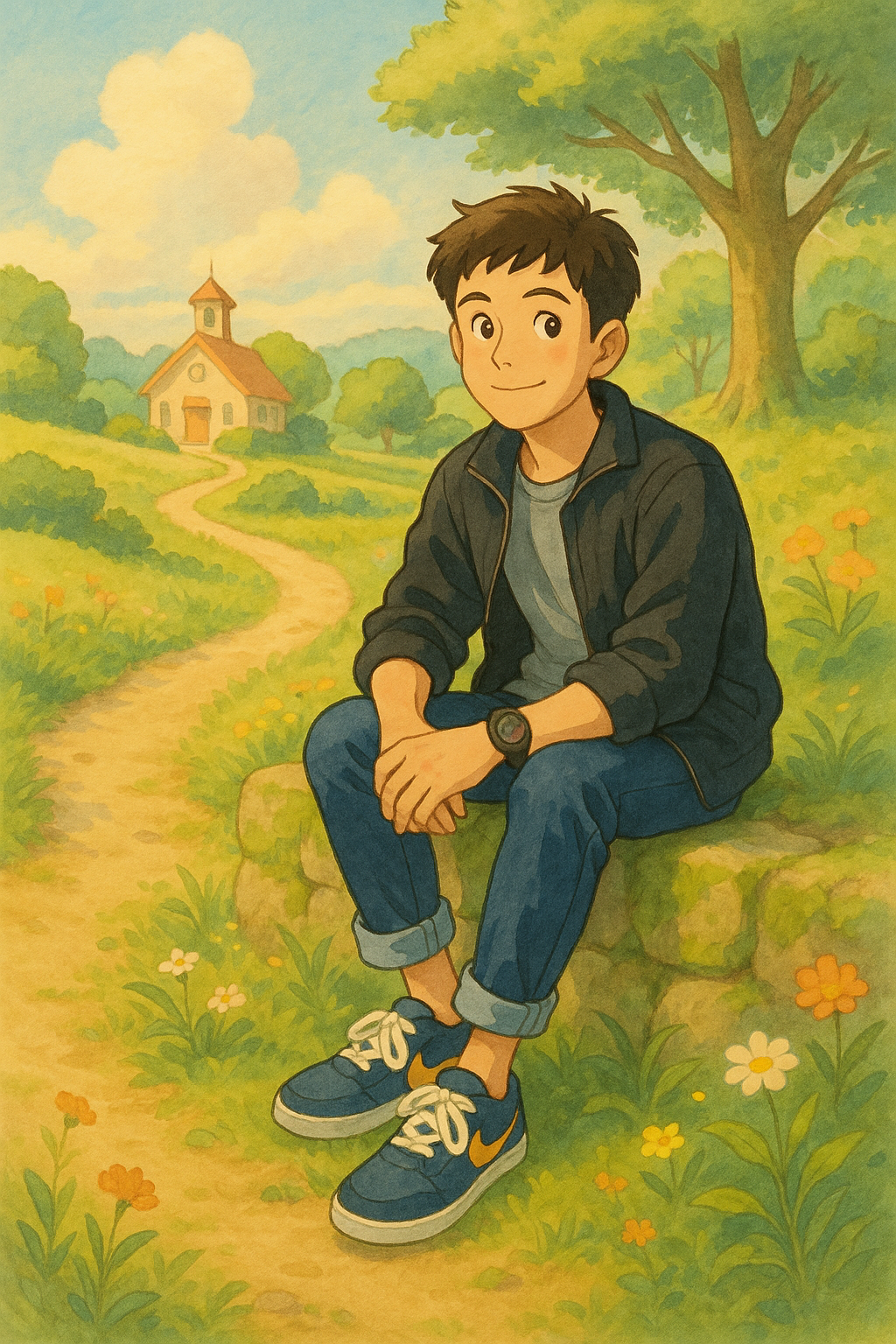
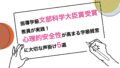

コメント