はじめに
教員の仕事でいちばん疲れるのは、授業でも行事でもなく、職員室の人間関係だ。
朝、ドアを開けた瞬間の空気でその日の気分が決まる。
挨拶のトーン、雑談の温度、誰かのため息。
そうした小さな揺れに、毎日心をすり減らしている教員は少なくない。
けれど、ここで立ち止まって考えたい。
なぜ、職員室の人間関係は、こんなにも私たちを左右するのだろう。
職員室は、教員にとって「もうひとつの教室」
職員室は、生徒がいないだけで、人間の集まる学びの場だ。
そこには、年齢も価値観も異なる教員たちが並んで座り、
一見同じ方向を向いていても、心の温度はバラバラだ。
若手教員は、「どう思われているか」に神経をすり減らす。
中堅教員は、板挟みの立場に悩む。
ベテラン教員は、後輩を支えたい気持ちと、距離感の難しさの間で揺れる。
つまり、職員室には人生のステージが重なっている。
それぞれの教員が、立場や思いを抱えながら、同じ空間を生きている。
人間関係のストレスは「相手の問題」ではなく「自分の解釈」
人間関係の悩みは、相手の言葉や態度から始まるように見える。
でも実際には、その出来事をどう受け取ったかがストレスの大部分をつくっている。
たとえば、同僚に「それ、やらなくていいんじゃない?」と言われたとする。
「批判された」と感じるか、「気遣ってくれた」と受け取るかで、
その後の気持ちはまったく違う。
相手がどういうつもりだったかより、
自分の“見方”が、職員室の空気を決めている。
だからこそ、まず整えるべきは「自分のレンズ」だ。
「職員室の空気」を変えるのは、立場じゃなく意識
職員室では、声の大きい人や影響力のある人が空気をつくるように見える。
けれど実際は、一人ひとりの小さな言葉や態度が積み重なって空気をつくっている。
たとえば、
・あいさつを一言多く返す
・「お疲れさま」と声をかける
・人の悪口にうなずかない
たったこれだけでも、周囲の雰囲気は少し変わる。
“空気をよくする側”に立つのは、経験年数ではなく意識だ。
それを続ける教員が一人いるだけで、職員室は確実に変わる。
「人間関係に悩む教員」は、人とまっすぐ関わろうとしている証拠
人間関係に悩む教員ほど、人に真剣だ。
同僚の言葉に傷つくのも、生徒に対して葛藤するのも、
「ちゃんと関わりたい」と思っているからこそだ。
だから、悩む自分を責める必要はない。
むしろ、それは教育の中心に“人”を置いている証拠だ。
仕事としての教育ではなく、
関係の中で育ち合う“営み”としての教育をしている。
職員室の人間関係をラクにする3つの視点
① 「合わない人がいて当たり前」と考える
学校は人の集まり。全員と分かり合うのは不可能。
違いを否定せず、「この人はこの人」と線を引こう。
② 「相手を変えようとしない」
相手を変えようとするほど関係はこじれる。
まずは自分の反応を整える。それが唯一コントロールできる部分。
③ 「小さな安心をつくる」
共感の一言、ねぎらいの笑顔、軽い冗談。
それだけで職員室の温度が上がる。
人間関係とは、正解のない連続実験だ。
成功も失敗も、すべてが学びになる。
「自分を整えること」が、職員室の平和の第一歩
結局、職員室の人間関係をよくする近道は、
相手を変えることではなく、自分を整えることだ。
疲れているときは、誰の言葉も刺さる。
余裕があるときは、同じ言葉でも笑って流せる。
職員室の空気を変える力は、
自分のコンディションにこそ宿っている。
だから、まず自分にやさしく。
その余白が、周りの人をもやさしくする。
終わりに──明日の職員室は、きっと少し違って見える
職員室の人間関係は、教員人生の大きなテーマだ。
逃げ場がないからこそ、心をすり減らす。
でも、見方をひとつ変えるだけで、
同じ風景がやわらかく見えることがある。
人との関係は、自分との関係でもある。
自分の中を整えながら働く教員が増えれば、
職員室も、学校も、少しずつ変わっていく。
明日、あなたがいつもの席に座るとき、
その空気がほんの少しだけ軽くなっているかもしれない
-1.png)
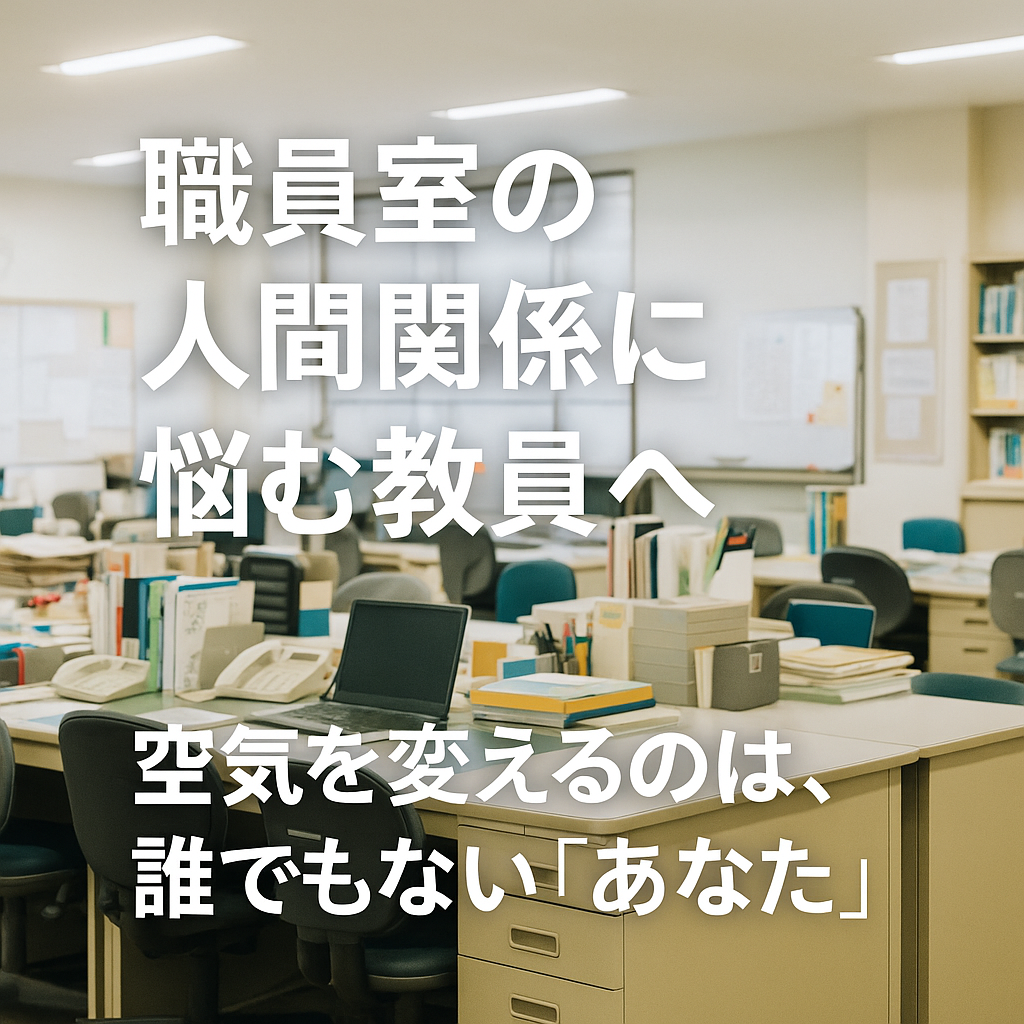

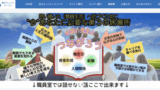
コメント