―信頼関係づくりの出発点は「体育」だった―
クラスの中には、
どうしても気になる子がいます。
やんちゃで言うことを聞かない子。
なかなか友だちと馴染めない子。
運動が苦手で、最初から
「やらない」と決めてしまう子。
そんな“あの子”に、どう関わればいいのか――。
学級経営に悩む先生の多くが、
きっと一度はこの壁にぶつかると思います。
私も、そのひとりでした。
■ 体育の授業が「信頼関係づくり」の場になる
「体育」と聞くと、体を動かす授業、
技術を教える時間という
イメージを持たれがちです。
しかし私にとっての体育は、
それ以上の意味を持っています。
体育の時間は、
子どもたちが“素”になれる時間です。
笑ったり、失敗したり、悔しがったり
――教室では見えない表情が
たくさん見られます。
だからこそ、
関係づくりのチャンスが
最も多い時間なのです。
特に、教室でトラブルを起こしやすい子や、
居場所を見つけにくい子にとって、
「体を動かす場面で認めてもらえる」
「できなくても受け入れてもらえる」
という経験は大きな意味をもちます。
体育の授業で
「この先生は自分を見てくれている」
と感じたとき、
その子との関係は、確実に動き出します。
■ 「できるかできないか」ではなく、「やろうとするかどうか」
私が体育で大切にしているのは、
“できたか”よりも
“やろうとしたか”を見取ることです。
なぜなら、苦手な子ほど
最初の一歩が重いからです。
例えば、縄跳びが苦手な子。
みんなが何十回も跳んでいる中で、
うまく跳べない自分を
見られるのはつらいものです。
でも、「縄を持って並んだ」
「1回だけでも挑戦した」――
この一歩をしっかり認めることが、
次への原動力になります。
そのために私は、
「できた・できない」ではなく、
「やってみた・工夫した・挑戦した」
という観点を子どもに
伝えるようにしています。
努力が見えるルールをつくることで、
苦手な子も安心して挑戦できます。
■ 苦手な子を“主役”にしない理由
よく
「苦手な子を主役にしてあげよう」
と言われます。
もちろんその考えも素敵です。
苦手な子にすれば、
自分にスポットを当てられるのは迷惑で
「放っておいて欲しい!!」
というのが正直な感想だと思います。
私は、特別扱いをすることが
本当の意味での包摂ではないと
思っています。
体育の時間に大切なのは、
苦手な子を目立たせることではなく、
苦手な子がいても
チームとしてマイナスにならない
ルールを設計することです。
例えば、チームで行うリレーやゲームで、
「どのチームが1番速く走れるか」
「どのチームが相手より得点できるか」
だけが価値になってしまうと、
どうしても苦手な子が
“足を引っ張る存在”になってしまいます。
でも、ルールを工夫すれば違います。
誰がいても勝敗の行方がわからない。
全員が自分の得意を発揮できる。
そんな設計にすれば、
苦手な子がいることが
自然なチームの一部になります。
「誰かの応援」や「見守り」などの
特別な役割を与えるのではなく、
その子がいても成り立つ
ルールそのものを考えることが、
教師の仕事だと思うのです。
特別な立場をつくるのではなく、
“誰もが無理なく混ざれる場”を
仕組みとしてつくる。
それが、苦手な子を排除しない
体育の在り方であり、
本当の意味で
「みんなでつくる授業」だと感じています。
■ 体育で育つ“関係の糸”
体育は、ただ体を動かす時間ではなく、
子どもたち同士、
そして教師と子どもをつなぐ
“関係の糸”を編む時間です。
一緒に転んで笑ったり、
うまくいかずに悔しがったり、
そんな体験の積み重ねが、
「先生は自分の気持ちをわかってくれる」
という信頼を生みます。
それがやがて、教室での声かけや
生活面の関わりにも波及していきます。
私は、体育で“あの子”の目が変わる瞬間を
何度も見てきました。
はじめは腕を組んで見ていた子が、
友だちの声に背中を押されて前に出る。
そして、自分でも驚くような笑顔を見せる。
そんな瞬間が訪れるたびに、
「体育の力」を感じます。
子どもたちは、
誰もが挑戦したい気持ちを持っています。
ただ、それを引き出す
“安心”が足りていないだけなのです。
体育は、その安心をつくる場になれる
――私はそう信じています。
■ 信頼関係の始まりは、「一緒に汗をかくこと」
教室でどんなに優しく声をかけても、
心の距離が縮まらないことがあります。
でも、体育で一緒に走ったり、
笑ったりするうちに、
気づけば“あの子”が
こちらを信頼してくれるようになる。
「先生、見て!」
「今日、ちょっとできた!」
そんな言葉が出てきたとき、
それは指導の成果ではなく、
関係ができた証です。
体育は、教師と子どもが
「並んで進む」唯一の授業かもしれません。
■ 体育から、学級経営を変える
学級経営における課題
――信頼関係、トラブル対応、
居場所づくり。
どれも根っこは同じです。
「自分を受け入れてもらえている」と
子どもが感じられるかどうか。
体育の授業は、
その感覚を育む最適な場です。
だから私は、
体育を学級経営の土台にすることを
大切にしています。
運動が得意な子も、苦手な子も、
支援が必要な子も、
同じルールの中でつながり、
互いを認め合う。
そんな体育ができたとき、
クラスの空気が変わります。
その空気が、教室に戻ってからの
“あの子”の表情を変えていきます。
■ 最後に――“あの子”の笑顔のために
体育は、「できる子“だけ”が輝く時間」
ではありません。
“あの子”が安心して
挑戦できる時間でありたい。
私はこれからも、
「どうすれば“あの子”が
やってみようと思えるか」
「どうすれば周りの子と
自然につながれるか」
そんな問いを大切に、
授業づくりを続けていきます。
体育の時間から、
子どもたちとの信頼関係を。
そして、“あの子”の笑顔が
クラス全体を照らすような、
そんな学級経営を
目指していきたいと思います。
-1.png)



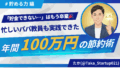
コメント