「なんでそんなに仕事終わらないの?民間じゃありえないよ?」
友人に言われたこの一言が、ずっと胸に刺さっている。
確かに、教師の仕事は際限がない。
授業、丸つけ、保護者対応、書類づくり、校務分掌……。
一つ終わったと思ったら、次の波が押し寄せてくる。
でも、あるとき気づいたんです。
「終わらない」のは、仕事量だけの問題じゃない。
“どこまでやるか”を、自分で決めていないことが原因なんだと。
今日はそんな気づきを、「働き方改革」という言葉にのせて整理してみます。
1. 丸つけが教えてくれた「終わらない構造」
教師の仕事の象徴といえば、「丸つけ」。
僕も初任の頃、子どもの頑張りに報いたくて、一人ひとりにコメントを書いていました。
でも、ある日ふと気づいた。
「丸つけって、どこまでやっても終わらないな」
誤答に✕をつける。
○と✕の両方をつける。
100点に花丸をつける。
間違いに解説を書く。
どれも“子どものため”には違いない。
だけど、それを続けていけば、時間はいくらあっても足りない。
教師の仕事は、自分の手でいくらでも増やせてしまう。
これこそが、「終わらない構造」の正体だった。
2. 「単位あたりの仕事量 × 人数 = 総仕事量」
たとえば、丸つけにかける時間を仮にこう設定してみる。
| 丸つけの方法 | 所要時間(1人) | 30人分の合計 |
|---|---|---|
| ✕だけ | 約5分 | 150分 |
| ○と✕ | 約8分 | 240分 |
| 花丸 | 約10分 | 300分 |
| 一人ひとりにコメント | 約15分 | 450分 |
わずか3分の違いで、90分の差が生まれる。
これを一度“見える化”してみたとき、衝撃を受けました。
つまり、教師の仕事量はこうして指数的に膨張する構造になっている。
3. 「どこまでやるか」を決める勇気
働き方改革というと、「仕事を減らそう」という話になりがちだけれど、
僕はそうじゃないと思う。
本質は、「どこまでやるかを自分で決めること」。
僕も昔は、全員のノートにびっしりコメントを書いていた。
でもあるとき、ふと自問した。
「このコメント、本当に子どもに届いているのかな?」
気づいたのは、子どもに響くのは量ではなく“タイミングと関係性”だということ。
例えば、価値付けに重きを置くならば、ノートを返す時に、そのよかったところをポンと伝える、あるいは書いている時に、机間巡視をし、その場で褒めることもできる。
だから僕は、“やる仕事”を減らし、“残す仕事”を選ぶようになった。
削ることは、怠けることではない。
「今、この瞬間に必要なもの」を見極めること。
4. 教師の働き方改革とは、「優先順位の再構築」
「子どものために」という言葉ほど、
教師を追い詰めてしまう言葉はないかもしれない。
もちろん、それは嘘ではない。
でも、それを“免罪符”にして、
自分を犠牲にし続けることが本当に子どものためだろうか?
僕は、「自分が健やかでいること」も子どものための一部だと思う。
働き方改革は、仕組みの問題じゃない。
自分自身の優先順位を取り戻すこと。
5. 「削ること」は、逃げではなく、選ぶこと
昔の僕は、すべての仕事を完璧にこなそうとしていた。
けれど今は、こう考えています。
削ぐことは、逃げではなく、選ぶこと。
彫刻家が、不要な部分を削りながら形をつくるように。
教師も、仕事を削ることで“自分らしい教育”を見つけていくのかもしれない。
時間も体力も有限。
だからこそ、
「ここまではやる」「ここからはやらない」
という線を引ける教師こそが、子どもに優しくなれる。
6. 終わりに──自己調整としての働き方改革
最近よく耳にする「自己調整学習」。
子どもが自分で学びを計画し、実行し、振り返り、改善していく力のこと。
でもそれは、教師にも必要な力だと思う。
働き方もまた、自己調整そのもの。
自分の現状を振り返り、改善を試みる。
その繰り返しが、学びにも人生にもつながっていく。
教師の働き方改革は、制度ではなく“生き方”の問題だと思う。
僕たちは、教室で「主体的に学ぶこと」を語っている。
ならば、自分の働き方も主体的に選ぶ教師でありたい。
それが、僕のたどり着いた答えです。
今日はこれでおしまい。
-1.png)

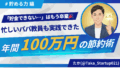
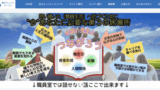
コメント